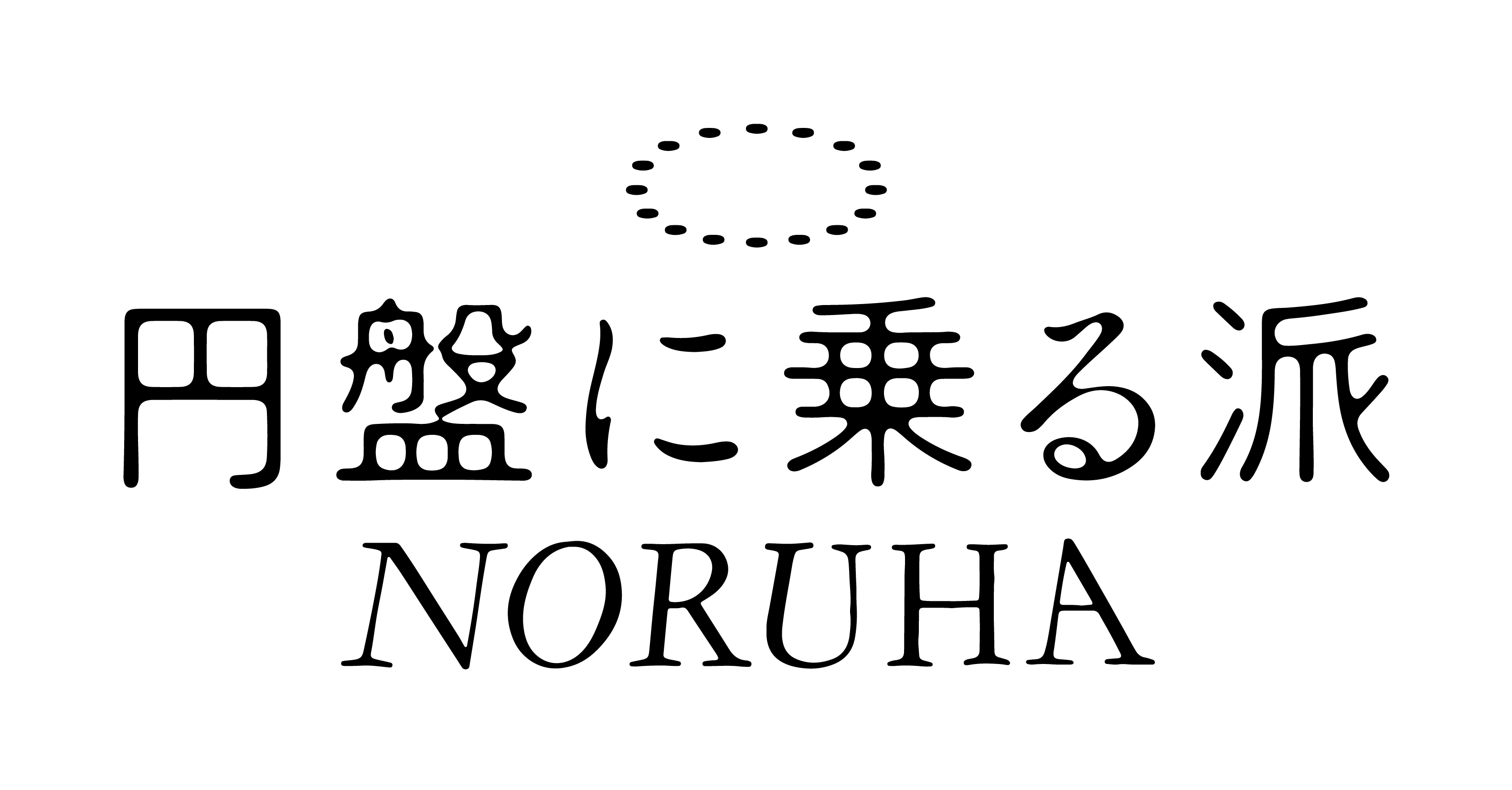––自己紹介をお願いします。
「円盤に乗る派」の代表で、今回『仮想的な失調』では劇作・演出を担当しているカゲヤマ気象台です。
––はじめに、『仮想的な失調』を再演するということについての印象からお伺いできたらと思います。
これまで、再演という形としては、「円盤に乗る派」の前身の「sons wo:」で2018年に初演した『流刑地エウロパ』という作品を、2021年のコロナ禍に再演したものがあります。あとはすごい昔に2010年ごろの作品を2年後とかに再演したことがあって、再演という形はそれぐらいかなと思います。
今回は、『仮想的な失調』の再演の依頼が来たときに、「円盤に乗る派」で会議をして、初演と同じ形でやるか、新しく作り直すかという話をしました。その時に、僕としては同じように上演したいと思った。一個は消極的な理由で、今から新しいアイデアを練り直して作り直すということが今の段階であんまりイメージがそこまで湧かなかったのと、芸術祭側からの期待に応えてやり切れる自信があんまりなかったということがあります。一方、 積極的な理由としては、2022年に初演をやった『仮想的な失調』という作品が、一体どういう作品だったのかということが自分の中でもまだ分からない部分として残っていました。それを改めて同じような形で再現して、今の時代と環境の観客に問い直した時に、『仮想的な失調』という作品がどういうものなのかということにもう少し深く接近できるんじゃないかと思って、その部分を追求してみたいという気持ちがありました。
『仮想的な失調』はいくつかの面で特殊な作品でした。一つは当時コロナの影響が大きく続いている中で、2022年になると社会的なルールとか制度が緩んできた状況でした。演劇界においても、それまでは感染症対策を徹底して公演を実施していたのが、少しずつ日常的にやれるようになってきて、やっとまた演劇ができるみたいな気持ちが重なったという意味で、まず状況が少し特殊でした。
もう一つは、蜂巣さんと二人で演出をしたということです。蜂巣さんと二人で演出をやるという体制を一番最初に取ったのは、2020年に吉祥寺シアターで上演した『おはようクラブ』という作品です。終わった後の反省とか振り返りを踏まえて、改めて二人で演出をやるという体制でやろうとなったのが『仮想的な失調』でした。一回やった反省を踏まえて臨んだんですが、それでも単純にブラッシュアップされて整理されたわけではなくて、また違った関係性やプロセスを選択したので、別種の想定していなかった事態が起きてしまって。『仮想的な失調』の初演が、一体どういうプロセスで出来上がったかというのはぐちゃぐちゃしてるんですね(笑)。作品として確かに成立したんだけど、どうやって出来上がったのか分からなくて。だからこそ作品としても独特なものが出来上がったと思っていて、しかも作品として評判が良かったことも不思議で(笑)。自分で不思議なものができたなと思ったものを面白かったと言われるのは自分としても不思議で、改めて出来上がった上演というものが一体なんだったのかを、再演を通して確かめたいと思っています。

––今回、東京芸術劇場での再演を作っていくにあたって、プロセスが分からないという部分はどのように解消しているんですか?
分からなさというのは、初演は新しく何かをつくるためのプロセスの中である種の齟齬みたいなものが起きていたということだと思います。今回は新しくつくるのではなく、一回つくったものを再現するという別のプロセスでやっているので、心持ちとして違います。
今回も演出家として二人がクレジットされていますが、気持ちとしては、初演で作った上演の演出に二人が関わっているから今回も同じようにしているという感じです。今回の現場でやっている作業としては、演出というより稽古場の仕切りみたいな気持ちが僕は割と強くて。例えば、海外でやったブロードウェイミュージカルを演出そのままで日本でやったりするじゃないですか。演出家は海外にいるけど、体感としての演出が同じというものを作る感じで、現場を仕切っている感覚があります。
––『仮想的な失調』は『船弁慶』と『名取川』をベースにしていると思うんですが、この二つにはどういった経緯でたどりついたんですか?
『船弁慶』に関しては、たまたまNHKの能の番組でやっているのを見て。『船弁慶』は少し変わった作品で、世阿弥の能とかは完成度も高くて最初から最後まできっちり作り込まれているんですけど、『船弁慶』に関しては少し後の時代に作られたものなので、構成がちょっと崩れているんですよね。しかもエンタメ寄りなんです。泣ける別れのシーンと、激しいアクションの戦うシーンをとりあえず二つやりました、面白いでしょ、みたいな感じで(笑)。全然関係ないシーンを二つやって、でも一つの作品ですという形にしていることに、ちょっと拍子抜けしたというかびっくりしたんです。まったく関係ないものが偶然並んでいるとか、ちゃんとした理屈とか必然性でものごとが繋がっていくのではなく、偶然変なものが紛れ込んでくる感じとか、そこに漂う存在の根拠の曖昧さとか不安感は、現代的な感覚だなと思ったんです。この構造を今の演劇にしたら面白いだろうなと思ったことが一つのきっかけでした。
『名取川』に関しては、これまで狂言を踏まえた作品を作ったら面白いんじゃないかという話が「円盤に乗る派」の中で出ていて。狂言のユーモアは「円盤に乗る派」の作品に通じるんじゃないかという話をしていて。「3Cs 2021 Tokyo: 変異する舞台芸術」という、アジア圏のいくつかの国のディレクターが、それぞれの国・地域からアーティストを呼んで創作をする交流企画に参加した時に、オンラインで作品を発表することになって、狂言を踏まえた作品を作ろうと決めて色々調べているうちに『名取川』に出会いました。元々は、狂言をやりたいというところから出発したんですが、『名取川』も話の筋としてはアイデンティティの希薄さにまつわるような話で。オンラインというのが存在感が希薄な状況なので、『名取川』で扱われるアイデンティティの曖昧さみたいな部分と相性がいいんじゃないかというプロセスでモチーフにしました。
––二つの古典を合わせているのが特徴的ですよね。テーマは共通する部分がありますが。
一個だけよりも二個やったほうが面白いなと思ったんですよ。共通する問題意識はあったのかもしれないけど、作家の勘が働いた感じがします。
––上演まであと1ヶ月くらいですが、今の心持ちはいかがですか?
稽古はすごく楽しくて、非常にいい稽古ができているなと思っています。座組のみんなも向かっている先がしっかりしていて、僕よりもみんなの方がビジョンがはっきりしてるんじゃないかなと思うくらい、みんなが作品に向かい合っているので、信頼がおけるメンバーで良かった、本当にありがたいなと思っています。
何かが立ち上がるんだろうということに対しては全く心配はしていなくて、今一番の不確定要素としては、実際の劇場空間というのが、実際に劇場に入ってみないとよく分からない部分が多い。東京芸術劇場のシアターウエストも、プロセニアムアーチ(額縁)が組まれていて、客席の構造もいわゆるお芝居を見るみたいな空気が非常に強い場所なので、実際に入った時にどういう風になっていくのかということが気になります。
あとはお客さんの数や雰囲気がちょっと予想できなくて。東京芸術祭の空気がどのように立ち上がっているかも予想がつかないところなので、楽しみな部分でもあります。
––今回が初めて「円盤に乗る派」を見る機会になる人も多いような気がしますね。
今回の『仮想的な失調』は東京芸術祭という枠組みもあって、チケット代が安めだったりアクセシビリティが充実していたりという点でもかなり見やすいものになると思います。今回はちょっと場所をお借りしているという雰囲気なんですが、我々は普段もっとよく分からない活動をやっていたりするので、これをきっかけに興味を持って我々のテリトリーに入ってきていただけたら、「円盤に乗る派」としては非常に嬉しいです。
2024年8月20日(火)
インタビュー・編集:中條玲
撮影:濱田晋