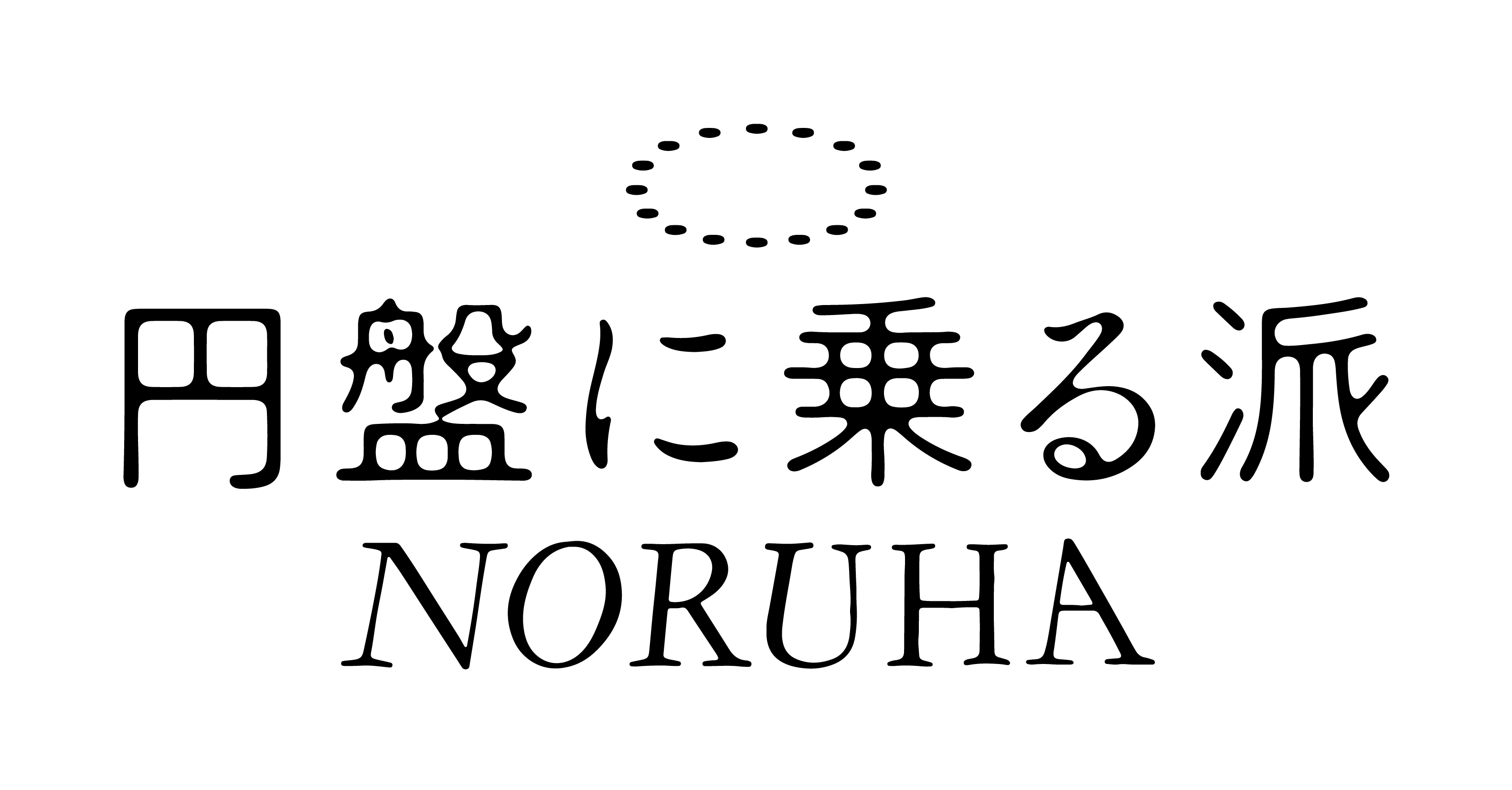円盤に乗る派の上演『仮想的な失調』の脚本(作:カゲヤマ気象台)を、このエッセイを書くにあたり上演よりも一足先に読ませていただいた。とても面白かった。面白かったのだけど、文字に対し文字で何かを論じたり内容に関しての考察を言語化したり、ということがどうしても苦手なので、読みながら思い出したこと、ここ最近の自分の身に起きていることを書いてみる。ひどく個人的な文章になってしまうことをお許しいただきたい。
私は映画を制作している。制作の場においての役割は監督(演出)である。ここ数年「俳優が<役柄>を獲得した際に生じる声の変化」「俳優その人自身と<役柄>との間の、どちらでもない声の生成」に対する興味を出発点として制作を続けていた。
どちらでもない声。それがどんな声なのか今ここでじょうずに書くことは出来ないが、本読みやリハーサルを重ねた末にふっと<その声>が現れたとき、その場にいるほとんど誰もがその出現に気が付く。空気の張りつめ方が変化するのだ。(声は音であり、それは空気の振動だからかもしれない。)突然ふっと顔を出すがずっと居続けることもしないその声は、幽霊に似た存在のように思える。音の重心はしっかりと下の方にあるので、いわゆる日本的な足のない幽霊とは、少しイメージが違う。もしかしたら声を発した俳優自身はその出現に気が付いていないかもしれない。そういった意味で憑依と言い換えることも出来るかもしれないが、その声は「どちらでもない」存在であり、乗っ取られている訳ではない。主体の在り処が判然としない、絶妙なバランスが保たれているときに現れるのだ。
7年程の時間をかけて「声」にまつわるアプローチを続けてきたのち、次作に取り掛かろうというさなかの今、最も興味があることは「顔」だ。
出来るだけ小さく、微細に表情筋を動かしてもらう中でスクリーン(画面/平面)に何が立ち現れるのか、もしくは、最小限の表情筋の動きだけで何かを出現させるために必要なものはなにか、という点に興味がある。人間の俳優に演じてもらわなくとも、なんなら人形劇で良いのかもしれない。とにかく筋肉は出来るだけ動かさないでほしい。筋肉を動かさずに何が伝えられるのか、そんなことに興味がある。
文楽における、人形遣いの目線の動きとまるで感情が宿っているかのような人形の表情の関係にも何かヒントがあるように思える。あの、何かを見ているようで何も見えていないような美しい人形遣いの視線の動きを作品のなかに落とし込みたい。そんな欲求がある。
その方法のひとつとして試してみたいことがある。それは2人の役者にひとつの役を演じてもらうことだ。いわゆるダブルキャストということではない。2人の役者が演じるひとつの役柄・人物を、同じ画面内に立ち上がらせることである。それぞれ異なるふたつの<私>が同一の<私>になるその時の、主体の在り処とその大きさのようなものを掴みたい。主体の在り処がひとつではなくふたつ以上の場所に点在した時、それぞれの演者の重心は、また、観る側の視点の置き場は一体どうなるのか。そのことが知りたいし、それをスクリーンに立ち上がらせたい。「私」(もしくはあなた)を「私(あなた)たらしめる」ものは一体何なのか。「声」から地続きに延びている未だ答えが掴めていないその問いを、模索し続けたいと考えている。
去年の秋から月に2回、決まった頻度で掛かりつけ医に通院をしている。きっかけは6月に始まった原因不明の発熱で、「いよいよコロナに罹ったか」と内科を受診したものの抗体検査は陰性。その後も37.5度程のイヤな感じの微熱が1週間以上続き再度PCR検査を受けるもやはり陰性。発熱そのものが辛いというよりも、自分の周りを覆っている空気と自分の身体との境界が判然としない曖昧な状態が薄ら気持ち悪かった。いま自分は暑いと感じているのか寒いと感じているのか、今日この場所がどれくらいの温度なのかがよく解らない。そんな状態が続いたかと思えば、突然顔から汗が吹き出し「暑いな」と思って扇風機を廻すと肌が風を受けた途端に耐え難い寒気を感じて震えが起きる、ということもあった。毎年連休明けから夏にかけて体調を崩しがちだった私は「ああこれは毎年起こるやつの酷い感じ。自律神経だな」と即座に考えたものの、それでも他の病気の可能性もあるかもしれないと数か月に渡りあらゆる病院へ足を運び、最終的に、現在通っている掛かりつけ医で「心因性発熱」と診断された。発熱は10月までほぼ絶え間なく続いたが、気候が涼しくなり始めてからは体温調節がだいぶしやすくなったことも手伝い、病院から出た薬を飲むとすぐ元通りの平熱に落ち着いた。(とはいえまた気温が上りはじめたことで、今年も安定しない体温と付き合いつつなんとか騙し騙し生活をしているのだが。)
この恒例の体調不良のせいで何年もこの時期の記憶は決まって朧気なのだが、殊に去年に関しては、そんな事情からか6月から10月までの記憶がほとんどない。人間が、実体を伴った「私」という状態をできる限り正常に保つためには、体温の安定がいかに大切なのかということを思い知った。安定した体温は世界との距離を一定に保ってくれる。体温が安定しないと自分の輪郭が曖昧になり、世界との距離、自分の身体の範囲が判らなくなる。上下する体温との格闘の日々は、自分自身の主体や重心の在り処も迷子にさせた。常に解けた状態で生きているような気分だった。
どこへ行くにも体温の証明を求められる日常がそこにはあった。いつでも発熱をしている私は、その場所の安寧を保つために<外部>との付き合いを断絶すべき存在となった。外出はほとんどせず世間との接触が断たれ、主体はますます行方不明になり気持ちもどんどん落ち込んでいった。
今は服薬により元通りの平熱と安定した気持ちを保てている。薬を飲まなくなったらまたあの状態に戻ってしまうのだろうか。薬を飲んでいない私は「私」ではなくなってしまうのだろうか。既にもう私はかつての「私」とは違う別の生き物になりつつあるのかもしれないが、再び服薬を止めたときの自我の変化が少し楽しみでもある。
『仮想的な失調』では、かつて名前を奪われた者(●●●)が9太郎という名を取り戻す。名を取り戻したばかりの9太郎の輪郭は、しばらくぼんやりとしている。主体の在り処が曖昧なように読める。
友人と、互いの最も古い記憶についての話をしたとき、私のそれが2歳の終わり頃であったのに対し友人は、生まれたばかりの、産院から退院するときの車内の光景を憶えていると言っていた。そのとき既に名前があったのかどうかすら定かではない、「私」であったのか判然としない輪郭の柔らかい曖昧な存在が持つ記憶。絶妙なバランスで主体を、現在・どちらでもない私に置くこと。そうして新しい声が生まれる。名前を呼んでもらう。(そういえば、赤ちゃんは大人よりも体温が高い。)
仮想(Virtual)の対義語のひとつにはPhysicalが含まれる。
『仮想的な失調』は演劇であり、お芝居だ。上演するにあたって役者は台詞をしっかりと身体に容れ、9太郎にこの後何が起き、どうなってしまうのかということをよく知っている。知っていながら、9太郎自身の未来が既に見えていながらも「現在の」「どちらでもない私の身体」に主体を置く。主体はやがて、役者の身体そのものから、その上演を見ている観客ひとりひとりの身体にも解けだしやって来る。その瞬間、上演という場が出来上がるのかもしれない。観客の一人として、そのときなにが起こるのかを目撃出来ればと思う。