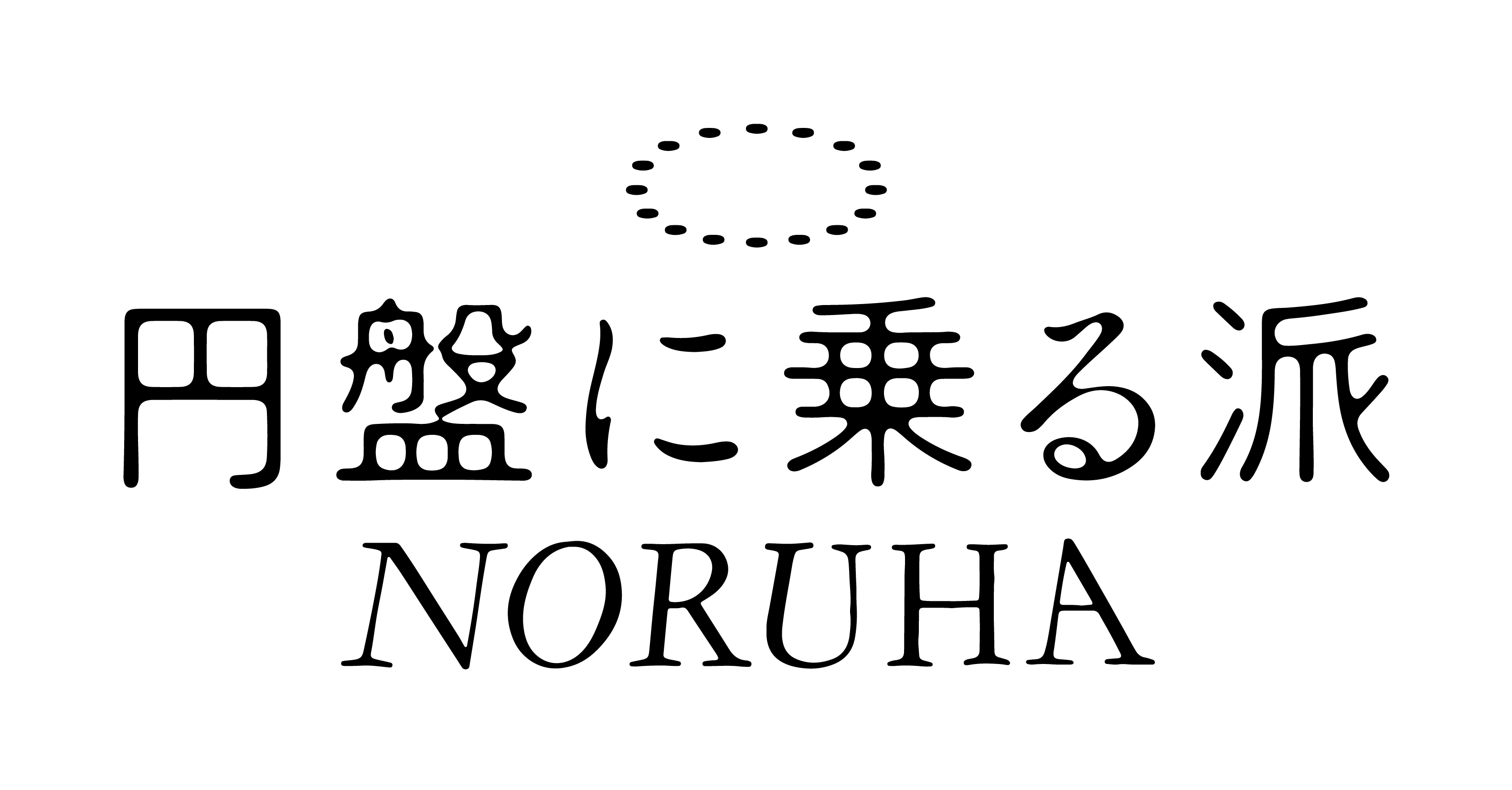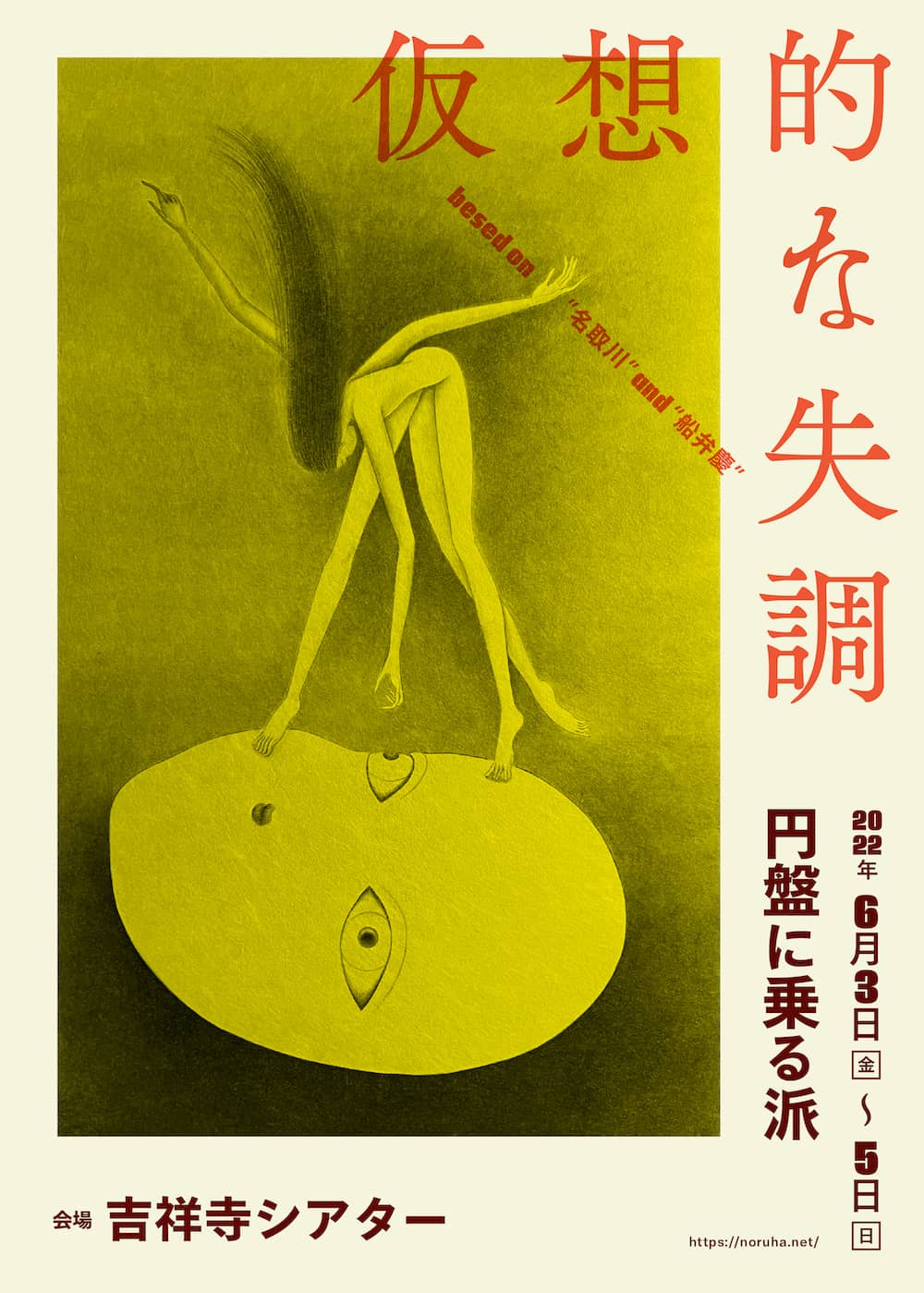
仮想的な失調(2022)
based on "名取川" and "船弁慶"
会期
会場
吉祥寺シアター
幽霊、自我の喪失、顔の見えない誰かの欲望……すべてが仮想的な時代における、物語の”失調”
寄稿エッセイ
戯曲『仮想的な失調』に寄せて、エッセイを執筆していただきました。
- 松田正隆(劇作家・演出家)
- 草野なつか(映画作家)
戯曲『仮想的な失調』販売中!
戯曲『仮想的な失調』の電子データを販売しております。円盤に乗る派webショップよりご購入ください。
https://noruha.stores.jp/
人々
-
1988年静岡県浜松市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。東京と浜松の二都市を拠点として活動する。 2008年に演劇プロジェクト「sons wo:」を設立。劇作・演出・音響デザインを手がける。2018年より「円盤に乗る派」に改名。2013年、『野良猫の首輪』でフェスティバル/トーキョー13公募プログラムに参加。2015年度よりセゾン文化財団セゾン・フェロー。2017年に『シティⅢ』で第17回AAF戯曲賞大賞受賞。
戯曲が要求する極限的な身体を引き出すことで、圧縮された「生の記憶」と観客が出会う場所を演出。
1989年生まれ。京都出身。2013年からより多くの劇作家、俳優に出会うため上京し、青年団演出部に所属。 また、庭師ジル・クレマンが『動いている庭』で提唱する新しい環境観に感銘を受け、「グループ・野原」を立ち上げる。
演劇/戯曲を庭と捉え、俳優の身体や言葉が強く生きる場として舞台上の「政治」を思考し、演出を手がける。円盤に乗る派、鳥公園にも参加し、演出、創作環境のブラッシュアップをともに考える。 -
1988年静岡県浜松市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。東京と浜松の二都市を拠点として活動する。 2008年に演劇プロジェクト「sons wo:」を設立。劇作・演出・音響デザインを手がける。2018年より「円盤に乗る派」に改名。2013年、『野良猫の首輪』でフェスティバル/トーキョー13公募プログラムに参加。2015年度よりセゾン文化財団セゾン・フェロー。2017年に『シティⅢ』で第17回AAF戯曲賞大賞受賞。
-
1985年生まれ 静岡県出身
新国立劇場演劇研修所三期終了。
柔軟性の高い身体性と声で大劇場から小劇場まで幅広く出演。俳優としての活動にとどまらず、ワークショップファシリテーターとしても活動中。七夕の短冊や手紙など身近な題材を使ったプログラムは、幅広い層に人気がある。最近では演技ともみほぐしの共通点に着目した『パフォーマンスもまれ処』や、美術モデルの経験から立ち上げたワークショップ『ポーズを着る』を展開。1993年生まれ 神奈川県出身。プリッシマ所属。
日本大学芸術学部演劇学科卒業後、劇団白昼夢を軸に活動。こまばアゴラ演劇学校 無隣館にも在籍した。主な出演作は、『麒麟大天覧』(石坂雷雨演出)、『現在地』(綾門優季演出)、『物の所有を学ぶ庭』(山本健介演出)、『ツヤマジケン』(屋代秀樹演出)、『流れる-能 “隅田川”より』(大塚健太郎演出)、『福井裕孝「デスクトップ・シアター」』(福井裕孝・吉野俊太郎演出)など。他に、映画「愛をたむけるよ」(団塚唯我監督)など。1988年生まれ。演出家/俳優。日本大学芸術学部演劇学科演出コース卒業。
2007年、ブルーノプロデュースを立ち上げ。2012〜15年、坂あがりスカラシップ対象者。近年の演出作品に青年団リンク キュイ『景観の邪魔』(2019)、青年団若手自主企画 櫻内企画『マッチ売りの少女』(2020)。これまでに生西康典、小田尚稔、田中功起、得地弘基、ミヤギフトシ、和田華子等の作品に出演。2019年からは批評家・ドラマトゥルクの山﨑健太とともにy/nとして舞台作品を発表。1987年生まれ 北海道出身。舞台芸術学院演劇部本科58期卒。
円盤に乗る派プロジェクトメンバー。俳優としてブルーノプロデュース、20歳の国、亜人間都市などの作品に出演。個人演劇ユニットPEOPLE太(ピープルフトシ)としてもゆるやかに活動中。1995年鳥取県生まれ。2019年より円盤に乗る派に参加。以降のすべての作品に出演。特技は料理、木登り、整理整頓、人を褒めること。人が集まって美味しいご飯を食べることが好き。下駄と美味しんぼに詳しい。
-
theater apartment complex libido:代表。演出家。omusubi 不動産 “まちのコーディネーター”
拠点を松戸市に定める中で、まちづくり会社を通して松戸での活動に従事している。演出業の傍ら、木ノ下歌舞伎、東京デスロック、ロロなどで舞台監督、演出部などにも携わり活動中。
-
1988年京都市生まれ。吉本有輝子氏に師事。
京都大学在学中より小劇場を中心として主に演劇とコンテンポラリーダンスの照明デザインを手がける。並行して2017年の閉館までアトリエ劇研スタッフルームに所属し、同劇場の運営に携わる。
近年は国外での活動も多く、これまでに10数カ国での公演に帯同している。
2020年度日本照明家協会賞新人賞受賞。
-
1992年生まれ お布団、青年団演出部所属
学生時代から都内小劇場を中心に舞台音響家として活動。
2016年以降、所属劇団のお布団での公演をきっかけに照明やその他のセクションの兼任をするようになる。
近年は自主企画等も行い、演劇のフィクション/ノンフィクション性について考えながら創作活動に携わっている。
-
1986年東京生まれ。建築構造設計・舞台美術家。
早稲田大学創造理工学部建築学科卒。
福島・NPO法人野馬土理事。京都・北山舎メンバー。
2017年よりグループ・野原に参画。在学時より自力建設を通した震災支援や海外WSを中心とした活動に関わり続け、設計事務所を経て現在にいたる。
風景と力に着目し活動を続けている。
舞台制作の過程をドローイングやスケッチでアーカイブ化し、創作につなげている。東京と山梨を往復しながら Multipotential の実践を続けている。
近年の舞台美術として、円盤に乗る派『おはようクラブ』(2020)グループ・野原『自由の国のイフィゲーニエ』(2021)、ヌトミック『ぼんやりブルース』(2022)などがある。
1999年千葉県生まれ。早稲田大学大学院創造理工研究科建築学専攻に在籍。小林恵吾研究室にて建築デザインを学んでいる。
人が持つ感覚や感情を追い、空間設計を通じて身体の内面にアプローチする方法を探っている。
-
大阪出身。衣裳家・俳優として活動。演劇をつくる団体「隣屋」所属。
国内外カンパニーの衣裳デザイン・製作・アシスタントなど。
物語から集めた様々なモチーフをつなぎ合わせ、規定されない人間像を立ち上げる。
身体の記憶を縫い合わせることをテーマに舞台上でリアルタイムで作品製作をするライブソーイングや、製作過程で発生したマテリアルによるグッズ製作も行う。
-
古典を手掛かりにしながら、内面化した同時代の無意識を想像上の「自画像」として描こうと試みる。最終的には愛に収束していく。デロリ石/センシュアルストーン。切株派。独楽が気になる。魚座。
-
1988年東京都生まれ。アートディレクター/グラフィックデザイナー。国内外でエディトリアル、音楽、ファッションなど多方面にて活動中。最近の仕事に「magazine ii(まがじんに)」アートディレクション、YOASOBI「三原色」ジャケットデザインなど。
-
デザイナー・音楽家。音楽・舞台・美術関連のグラフィックデザインを主として受け持つ。2016年より横須賀のオルタナティブ古民家・飯島商店を拠点に活動中。
takararamahaya.com -
1988年埼玉県生。桜美林大学在学中に制作として舞台芸術に携わり始める。2010年よりOrt-d.d(現・Theatre Ort)に在籍し退団。その後はフリーランスとして(劇)ヤリナゲ、sons wo:モモンガ・コンプレックスなどの公演で制作を担当。小劇場作品の他にも、彩の国さいたま芸術劇場等の公共ホール事業に参加するなど、ジャンルや規模にこだわらず活動している。
-
2000年東京生まれ神奈川育ち。2022年3月に桜美林大学を卒業後、フリーランスの制作になる。
大学在学中は図書館や幼稚園で公演をするなど劇場に囚われない活動も行ってきた。
これまでに劇団鹿殺し、EPOCH MAN、劇団しようよなどの作品に参加。
- 主催
- 円盤に乗る派
- 提携
- 公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団
- 協力
-
お布団、グループ・野原、劇団白昼夢、青年団、隣屋、PEOPLE太、プリッシマ、ブルーノプロデュース、y/n
有楽町アートアーバニズムプログラムYAU、一般社団法人ベンチ - 助成
- 公益財団法人セゾン文化財団
![]()
![]()
料金
前売 一般 3,000円 U25 2,500円 アルテ友の会会員 2,500円(武蔵野文化生涯学習事業団のみ取扱) 当日 3,500円 ※日時指定、全席自由、税込 ※U25チケットは入場時に年齢確認証が必要です。
チケット
円盤に乗る派shop:https://noruha.stores.jp/
イープラス:https://eplus.jp/sf/detail/3618990001-P0030001
武蔵野文化生涯学習事業団:0422-54-2011(9:00~22:00)
お問い合わせ
050-3631-4380
info@noruha.net