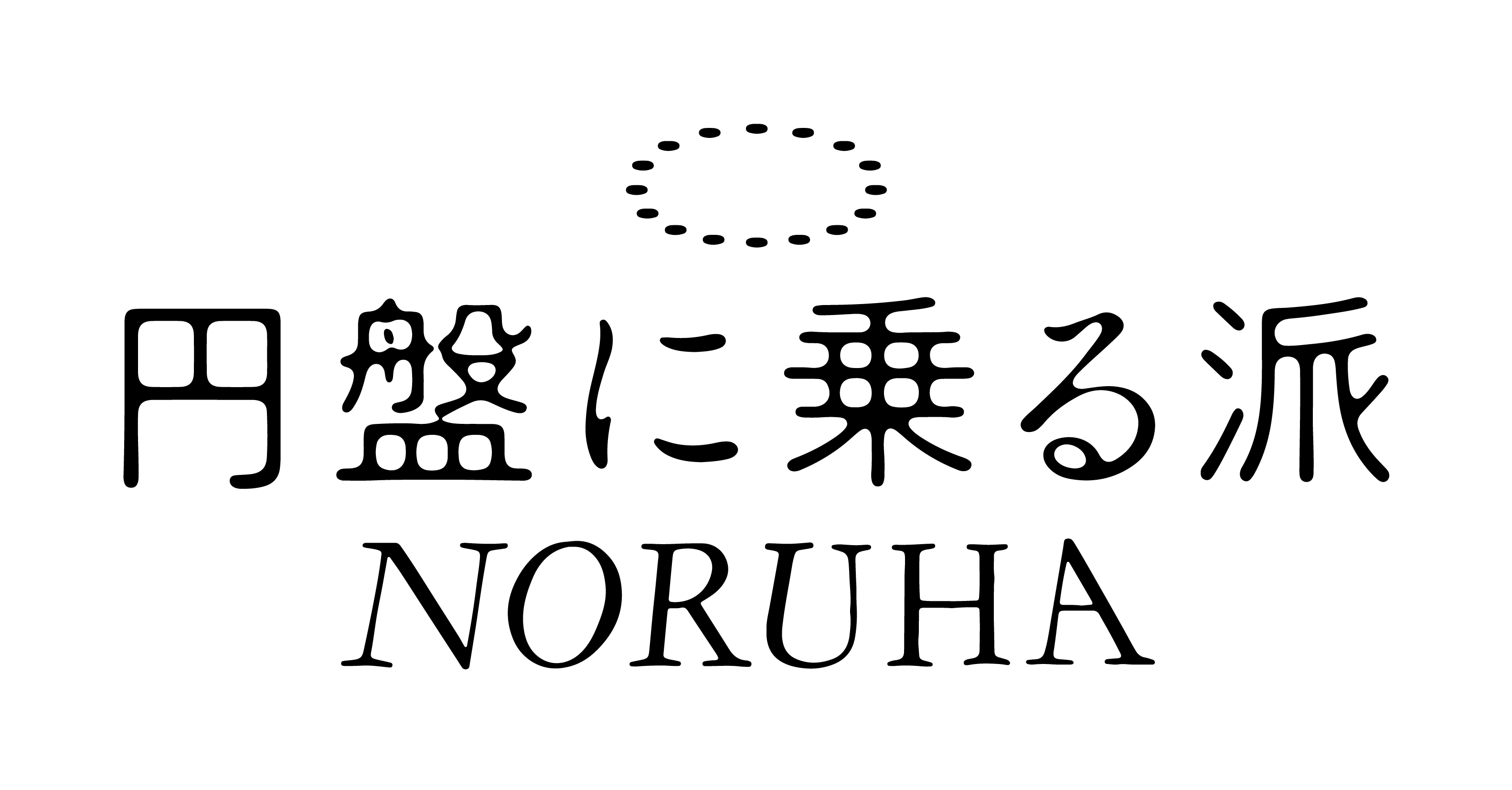こちらの劇評は、2022年に吉祥寺シアターで実施した上演に対するものであり、今回の再演では演出面において一部変更が生じる部分があります。また、テキスト内で上演の内容に深く言及する部分がございます。ご了承ください。
2022年6月、吉祥寺シアターにて円盤に乗る派『仮想的な失調』を見た後の、いいバンドのライブを聞いてきたような、身体に残る観劇後の感覚はよく覚えている。今回、劇評を執筆するにあたって、当時の観劇を思い出しながら、その記憶を上演映像で補完した。
初めに断っておくが、私は円盤に乗る派の、理想的な観客ではないかもしれない。これまでいくつか、円盤に乗る派の作品を見てきたが、カゲヤマ気象台の詩的かつユーモアある戯曲と、俳優たちの多様で豊かな身体性を評価しつつも、ある種の「乗れない」感覚を覚えることもあった。だが、本作は私にとって「乗れる」作品へと仕上がっていた。「乗れる」「乗れない」は主観的な感想であると理解しつつ、本稿ではこの感覚をベースに、この作品を紐解いていきたい。
『仮想的な失調』は、狂言の『名取川』および能の『船弁慶』を基にしている。戯曲を執筆したカゲヤマ気象台は、2作の大まかな筋をベースにしつつ、設定は大幅に変えている。簡単にあらすじから見ていこう。
まずは冒頭、幽霊によって一人の男の魂が体を得るシーンが挿入される。幽霊は、オープンワールドゲームのチュートリアルのように、身体の使い方や、物事の対処の仕方を男に伝える。この謎めいた登場人物である幽霊は、本作を通じて要所要所に現れるのだが、その男の過去であり、また同時に未来でもあり、男の身にこれから起こることを既に知っている。ACT Ⅰは狂言『名取川』を基にしている。原作では自分の名前を覚えられない男の話だが、本作ではハッピーマートというコンビニエンスストアを舞台として、なとりという名前の店員と、名前を取られたと主張する客の言い争いを描く。
続くACT ⅡとⅢは、能『船弁慶』を基にしている。この作品は、前場と後場で全く異なった情景を描いている。前場は兄である頼朝に追われることとなった義経(九郎)が、困難な道のりを連れていくことのできない愛妾・静御前(前シテ)と別れる様を描き、後場では、大物の浦から西国へ向かう船上にて、源氏によって死へと追いやられた、平家の総大将・知盛の霊(後シテ)と義経・弁慶の戦いを描く。『仮想的な失調』では、義経・弁慶・静御前が、それぞれ9太郎・ムサシ丸・シズチャンと名前を変えている。9太郎は、兄によってネット上に画像を晒され、炎上していた。そのため、違う街へ移住しようとするが、道中のゲストハウスで、飼犬であるシズチャンとは別れることとなる。その後、トラブルがあり、まずは一人で電車で行くことになった9太郎だったが、車内で謎の男に襲われ、重傷を負い、病院へ運ばれる。幽霊が言うには、その謎の男は、9太郎と兄が、過去にネットで炎上させて、川で死んだヒラオカクンの霊だという。
多様な演技体
本作に限らず、円盤に乗る派作品の一般的な特徴として挙げられると思うが、それぞれの俳優の演技体に統一感がない。俳優たちの演技は、新劇でもなければ現代口語演劇でもない、独特の様式感を持っていて、そのスタイルはそれぞれ異なっている。それぞれの俳優の演技について、その特徴を概観していこう。
前述したように、冒頭、幽霊によって、ある魂が日和下駄という俳優に受肉するシーンから始まる。日和は、可動範囲を確かめるかのように、顔をさまざまな形に引き延ばす。私は、VRゴーグルをかけたVRChatの世界を想像した。ゴーグルをかけると見知らぬ世界が広がっていて、その世界に入った人は、身体をどう動かすのか、まずは学ばなければいけない。その後、ACT Ⅰの彼は、Citizen(鶴田理沙)と出会い話すが、その世界のルールが分からず、相手に言われたことに過剰に反応したり、突発的に感情が爆発したりする。『名取川』を基にしたACT Ⅰが終わり、ACT Ⅱからシームレスに『船弁慶』を基にした話が始まるが、日和は役の変化についていけない。彼は、自分がその世界で何の役を演じているのか、他の人に確認しながら、自分が9太郎と呼ばれており、事件に巻き込まれていることを知る。いわば、物語の中で果たすべき役割を受動的に学ぶのだ。それゆえ、彼は物語の中心人物でありながら、ムサシ丸、シズチャンに言われるままに、受動的に物語が進んでいく。
鶴田理沙は、Act 1(「名取川」)では道端で会うCitizen、ACT ⅡとⅢ(「船弁慶」)ではゲストハウスのOwnerという役を演じるが、その名の通り抽象的な市民、オーナーという役割を担っている。彼女の演技は、古典的なドラゴンクエストを代表とするようなRPGゲームの村人などのNPC(ノンプレイヤーキャラクター)を想起させる。「ある特定の情報をプレイヤーに伝える」という限りにおいて、NPCは親身になってくれる存在である。しかし、ゲームの中のNPC同様、鶴田が演じる役は、どこか心から話していないように聞こえ、音量や声の方向もどこか不自然だ。
橋本清は、ACT Ⅰではなとり(傍点)役、ACT ⅡとⅢ(「船弁慶」)ではムサシ丸を演じる。彼の話し方は、どこかの方言を想起させつつ、しかしどこのものでもないだろうと確信できるような、複雑なアクセントによる変拍子で刻まれる。ビートは奇妙なリズムの身体の動きと共鳴し、独特なユーモアを醸し出す。
畠山峻は、ACT ⅡとⅢ(「船弁慶」)でシズチャンとヒラオカクンを演じる。(原作の能における前シテ・後シテに対応している)シズチャンは、犬でありながら、責任感のある友人役といった演技ではっきりと話し、自分の意見を述べるため、ゲストハウスでオーナーから犬と指摘されるまで、はっきりと犬と断定することはできない。座組の中でも、観客が慣れ親しんだ、いわゆる演劇的な発話で話すシズチャンだが、それが犬だということとのコントラストがおかしい。彼の真骨頂は、ポーティスヘッドの妖しいダウナーな『サワー・タイムス』に合わせて踊る別れの舞だ。井森美幸を彷彿とさせるジャズダンスの仕上がりは、観客の想像の斜め上をいく。少し脱線するが、市原佐都子作・演出の『バッコスの信女―ホルスタインの雌』に登場する犬と共に、近年の演劇界で特徴的かつ魅力的な犬役だと思う。
最後に、謎めいた幽霊役の辻村優子だ。この幽霊は『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のナビィのように、日和に付き添い、勇気づけ、警告を送る。何やらゲームの連想が多くなってきているが、本作はゲームを思わせる構造や役、セリフ回しが散りばめられている。幽霊は、はきはきと喋るものの、喋り方は単調でどこか温度がなく、AIによる読み上げた文章を想起させる。辻村という優れた俳優が、制御してこのような発話をしていることは言うまでもない。
以上のように、多様な演技体を持つ『仮想的な失調』のアンサンブルは、本作がベースとする伝統芸能のような、強い統一感のある身体や発声を持たない。それゆえ、舞台上の俳優たちのやりとりは、内容だけでなく、演技体としてもどこかちぐはぐなことが多い。しかし、それゆえにジャズのセッションがそれぞれの楽器の特性を活かして演奏するような、音楽的な愉しさがある。
視覚・聴覚が生み出すリズムの総合
本作に通底する独特なリズムは、舞台上の俳優たちの声や演じ方のみによって作られるわけではない。原作である狂言・能とのズレも、観客の予期するものをいい意味で裏切りながら、本作に特有の、観客を弛緩した状態に留めるようなリズムを作り出していると言えるだろう。演技に関しては前述した通り、伝統芸能とは大きく異なるが、特にACT Ⅱ以降の『船弁慶』で見られるように、本作と原作の名前の間の距離感も絶妙だ。原作の義経(九郎)・武蔵坊弁慶・静御前の3人は、本作では9太郎・ムサシ丸・シズチャンと名付けられている。原作の厳めしい名前に反して、お笑い芸人の名前を想起するような本作の名前は、呼ばれる度に脱力した笑いを伴う。
また、視覚的なリズムも忘れてはならない。スマートフォンのスワイプのように、台車に乗って登場する小道具や舞台美術、ノイズと共に、ゆっくりと開く舞台後方の搬入用のシャッター、そして現れる重量感のある本物の車―。渡邊織音による舞台美術も、ただ劇の進行に仕えるだけでなく、舞台美術それ自体が、自立してリズムを作り出す。衣装も、それぞれのキャラクターの持つ独特なリズムを、視覚的に補完する。裏地が表面に来ているようなムサシ丸のコート、9太郎の着るフィッシングベスト、幽霊の履く白い長靴、シズチャンの着るアーガイル模様の反復―。衣装はキャラクターの個性と響き合うか、もしくは不協和音を生み出す。このように、原作とのズレや、視覚・聴覚が生み出す独特なリズムの総合がこの上演を作り上げていると言えるだろう。
観客をチルさせる演劇
本作のように、多様な演技体で構成される演劇は、伝統芸能のように、統一的で強度の高い身体性を要求するような形式とは大きく異なる。これは何も伝統演劇だけではない。一般に、劇の進行に責任を持つ演出家にとって、ある一つの美的な方向へ俳優を誘い、作品を練り上げることは重要な仕事である。その練り上げられた強度を持って、観客を劇に集中させるのだ。円盤に乗る派は―おそらく「派」としてのフラットな集団性がこれを可能にしているのだと思うが―どこか集中という概念からは縁遠い。むしろ、多様な音、声、演技、美術で、劇の「芯」を解体していき、観客の意識を分散させる。冒頭で、あくまで個人的な感想として、円盤に乗る派の作品には「乗れる」作品と「乗れない」作品があると述べたが、その原因の一端は、円盤に乗る派作品の、観客の意識を分散させていくような構造にあると思う。
しかし、本作が「乗れる」作品であるというのは、必ずしも私個人だけでもないようだ。事実、本作は2022年の吉祥寺シアターでの初演の成功後、東京芸術祭2024のプログラムにラインナップされている。観客の意識を分散させながら、そこから生み出した新たなグルーヴが、観客の身体に共振したのだろう。本作は観客を熱狂させる演劇ではなく、むしろ日々の生活で火照った観客の体を「チル」させるような作品である。心地よいリズムに、体を横に揺らしながら、舞台上の俳優に耳を澄ますこと。これこそまさに演劇の醍醐味だ。